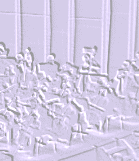チャイコフスキー最後のそして、自身「最高の作品」とした交響曲第6番を創造し、これを「パセティーク」と呼称。これは「悲愴」もいうべき意味合いで。情熱、愛、希望、勝利、そして避けられない死について、音楽で世に問いかけたものです。1893年10月16日自身の手で初演の後、わずか9日後にコレラにより急死しようとは!これにより悲愴はより象徴的意味合いを持つことになりました。彼はこの時56歳、ロシアを代表する音楽家として名声を得るも、その道のりは平坦なものではなく、とりわけ愛情問題では苦労の連続でした。愛情の対象は男性であるにもかかわらず、当時同性愛は世の中で認知、許容されるものではありません。年齢差のある教え子の女性と仮初めの結婚をするも、すぐに破綻し相手の女性を傷つける結果ともなり、深く自責の念にかられます。人を愛しつつも世に受け入れられない自身の心、その葛藤と行く末を音楽に託し、昇華させていった彼の独白ともいえる側面をもつ傑作交響曲です。 第1楽章は序奏付き付きソナタ形式。コントラバスの半音階下降の上でファゴットが陰鬱な旋律を奏でヴィオラが呼応します。やがて第1主題がヴィオラによりリズミカルに奏され、徐々に緊張感を帯びつつ劇的に盛り上がります。収まると甘美かつ憂いを含んだ第2主題がヴァイオリンとチェロで歌われます。。このメロディーが木管と弦で行きつ戻りつした後にファゴットが最弱音で閉じます。突如大音量でオーケストラ全体が鳴り響き強烈で戦闘的な音楽が進行します。展開部では第1主題が次々と現れ高揚していきます。そしてクライマックスが嘆きを帯びた咆哮で終わると、第2主題が情感を込めて歌われつつ穏やかに楽章は締めくくられます。 第2楽章は4分の5拍子という混合拍子のワルツ。スラブ音楽にはよくみられる拍子です。冒頭チェロが旋律を奏でますが、この優雅でありながら影のある旋律が交錯していきます。中間部はティンパニが規則正しく拍を刻む上で木管、弦楽器が一層不安気で寂しげな旋律を奏でます。再現部では主題のワルツが回想されていき曲を終えます。 第3楽章はスケルツォ的な楽想から始まっていき行進曲に変容していきます。性格の異なる音楽が交互に登場しつつ前へ前へと進みつつ音楽が高揚していき、最後は劇的かつ破滅的なクライマックスを迎え楽章は終えます。 第4楽章、冒頭の主題は「ファー♯・ミレ・ドー♯・シ・ドー♯」という旋律ですが、これは弦楽器群が交互に音を刻みかつ融合するという独自なもの。人間関係に悩みぬいた彼の心情が吐露されているようです。それを乗り越えた彼の思いは愛情あふれる第2主題に到達します。やがて金管楽器が加わり、小クライマックスをむかえた後に第1主題がヴァイオリンのみで明確に奏されます。主題が高揚しオーケストラ全体が最大のクライマックスに到達すると、その後は音の次元を超越した世界の向こうへと静かに進み。消え入ります。 まさにチャイコフスキー音楽の集大成であり、かつ19世紀音楽の終着点がここに極まっています。