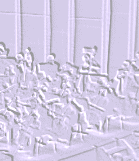ムソルグスキー;交響詩「はげ山の一夜」
ムソルグスキーは地主の息子としてサンクトペテルブルク近郊に生まれます。母からピアノの手ほどきを受け音楽に目覚め、士官として役人仕事をしつつ作曲活動をおこない、音楽を貴族から民衆へとというバラキレフらの活動に共鳴して、いわゆる「ロシア五人組」の一人として活躍しますが、理想と現実のギャップからか飲酒に溺れ、仕事も失い悲惨な最後を遂げました。しかしその彼により生み出された音楽は心に強く訴えるインパクトを持ち、後世への影響も大きいものがあります。代表作である交響詩「はげ山の一夜」は1860年頃に、メグデン男爵の戯曲「魔女」の一場面たる「はげ山のヨハネの祭り」を表現する音楽として構想されものの頓挫。その後他のオペラ作品に転用を図るも成就せず。彼の死後、リムスキーコルサコフが改訂をしたうえで1886年初演され、広く知られるようになりました。総譜には「地下の闇に響く不思議な声、闇の精、闇の神チェルノボーグが出現し、魔物の饗宴が繰り広げられる。やがて教会の鐘がなり、夜明けとともに闇の魔物は消え去る」と記されており、楽曲はその物語に沿って、不気味な闇の世界にて魔物達の乱痴気騒ぎの果て、鐘が鳴り響き、朝の光で世界が浄化されます。